
|
図3.1に示すように望遠鏡や顕微鏡などの光学機器では、対物レンズに入射した光線が接眼レンズを出たところに生ずる光線束は、その約10mmくらい後方で最もくびれる。これを射出瞳という。例えば、望遠鏡を手を伸ばして持ち、接眼レンズの中央を見ると3〜5mmくらいの径で明るく見える部分があるが、これが射出瞳である。
さて、望遠鏡を使用して観測する場合には、眼の入射瞳をほぼ望遠鏡の射出瞳に置くことが重要である、そうすることによって望遠鏡の全視野を構成する光線束が眼に入って、視野全体を欠くことなく見ることができるからである。この射出瞳の位置を「アイ・ポイント」という。眼を接眼レンズに近付け過ぎたり、離し過ぎたり、あるいは左右にずらしたりすると光線束の一部は眼の入射瞳を通らなくなって視野の一部が見えなくなる。
3.2 望遠鏡の倍率
望遠鏡は図3.2に示すように焦点距離f1の対物レンズAと、f2の接眼レンズBを組み合わせた共軸レンズ系で、十分焦点距離の長い対物レンズを用いて遠距離にある物体の大きい実像を得ようとするものである。
望遠鏡の倍率Γは
Γ=f1/f
で表される。
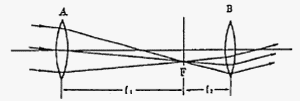
図3.2 望遠鏡の倍率
3.3望遠鏡の能率
望遠鏡の能率Lは、裸眼で見る場合の視力Saに対する望遠鏡を通して観測する際の視力Sfとの割合であり
L。甦a/Sf
で表される。
この場合、SaおよびSfはそのときに見えた対象物の角度分で表された大きさの逆数値で表される。そして能率Lは対物レンズの直径、倍率、透過度、視域の輝度およびコントラスト、並びに二・三の個人的定数(例えば観測者の瞳孔の径など)の関数であることがわかる。
ドイツのA.キュール(A.Kuhl)はこの望遠鏡の能率Lを経験的に近似式で表した。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|